はじめに
今回も、応用情報技術者試験の過去問を解いていきます。
今回は 「AI(人工知能)」分野から「ディープラーニング」 に関する問題を取り上げます。
最近のIT動向でもよく出てくるテーマなので、しっかり押さえておきたいですね。
問題(R6年度 応用情報技術者試験 春期 午前 問3)
問3 AIにおけるディープラーニングに関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア あるデータから結果を求める処理を、人間の脳神経回路のように多層の処理を重ねることによって、複雑な判断をできるようにする。
イ 大量のデータからまだ知られていない新たな規則や仮説を発見するために、想定値から大きく外れている例外事項を取り除きながら分析を繰り返す手法である。
ウ 多様なデータや大量のデータに対して、三段論法、統計的手法やパターン認識手法を組み合わせることによって、高度なデータ分析を行う手法である。
エ 知識がルールに従って表現されており、演繹手法を利用した推論によって有意な結論を導く手法である。
解答
正解:ア
解説
ディープラーニング(Deep Learning) とは、AI分野の中でも 機械学習 に属する手法のひとつです。
特徴は ニューラルネットワーク(神経回路)を多層化 すること。
この「多層(deep)」な構造により、
画像・音声・言語といった複雑なデータから 高次の特徴を自動的に抽出し、認識・分類 が可能になります。
正解の アの選択肢 はまさにこの特徴を簡潔に述べたものとなっています。
他の選択肢の解説
| 選択肢 | 内容・解説 |
|---|---|
| イ | 「大量のデータから新たな規則や仮説を発見する」 という点はデータマイニングや統計的手法に近く、外れ値除去はディープラーニングの本質ではない。 |
| ウ | 「三段論法」 は演繹的な推論法であり、ディープラーニングは帰納的な学習(データからパターンを発見)なので違う。パターン認識は行うが、三段論法との組合せは本質的ではない。 |
| エ | これは 「エキスパートシステム」 と呼ばれる古典的AIの考え方(ルールベースAI)で、ディープラーニングとは異なるアプローチ。 |
問題の用語解説
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 人工知能(AI) | 知的なふるまいをするシステムの総称 |
| 機械学習(Machine Learning) | AIの中で、データからルールやパターンを学習する手法群 |
| ディープラーニング(Deep Learning) | 機械学習の中でも、ニューラルネットワークを多層化した手法 |
| ニューラルネットワーク | 人間の脳神経を模倣した情報処理の仕組み |
体系的位置づけ
今回のテーマ「ディープラーニング」が
応用情報技術者試験の中でどこに位置づけられるのかを整理します。

出題範囲:テクノロジ系 → 人工知能分野 → 機械学習・ディープラーニング に分類されます。
ITの基礎理論に近いテーマですが、近年の技術動向が反映されやすい部分でもあります。
まとめ
今回はディープラーニングの基礎的な問題を扱いました。
AI関連分野は出題傾向が新しいテーマに寄るため、
「今の技術トレンドを理解する」意識を持って学習するのが重要ですね。
このような過去問を解きながら、
用語の正確な理解+技術の背景まで学ぶことを意識して進めていきましょう。
参考情報
- IPA 応用情報技術者試験 過去問題:
https://www.ipa.go.jp/shiken/mondai-kaiotu/2024r06.html
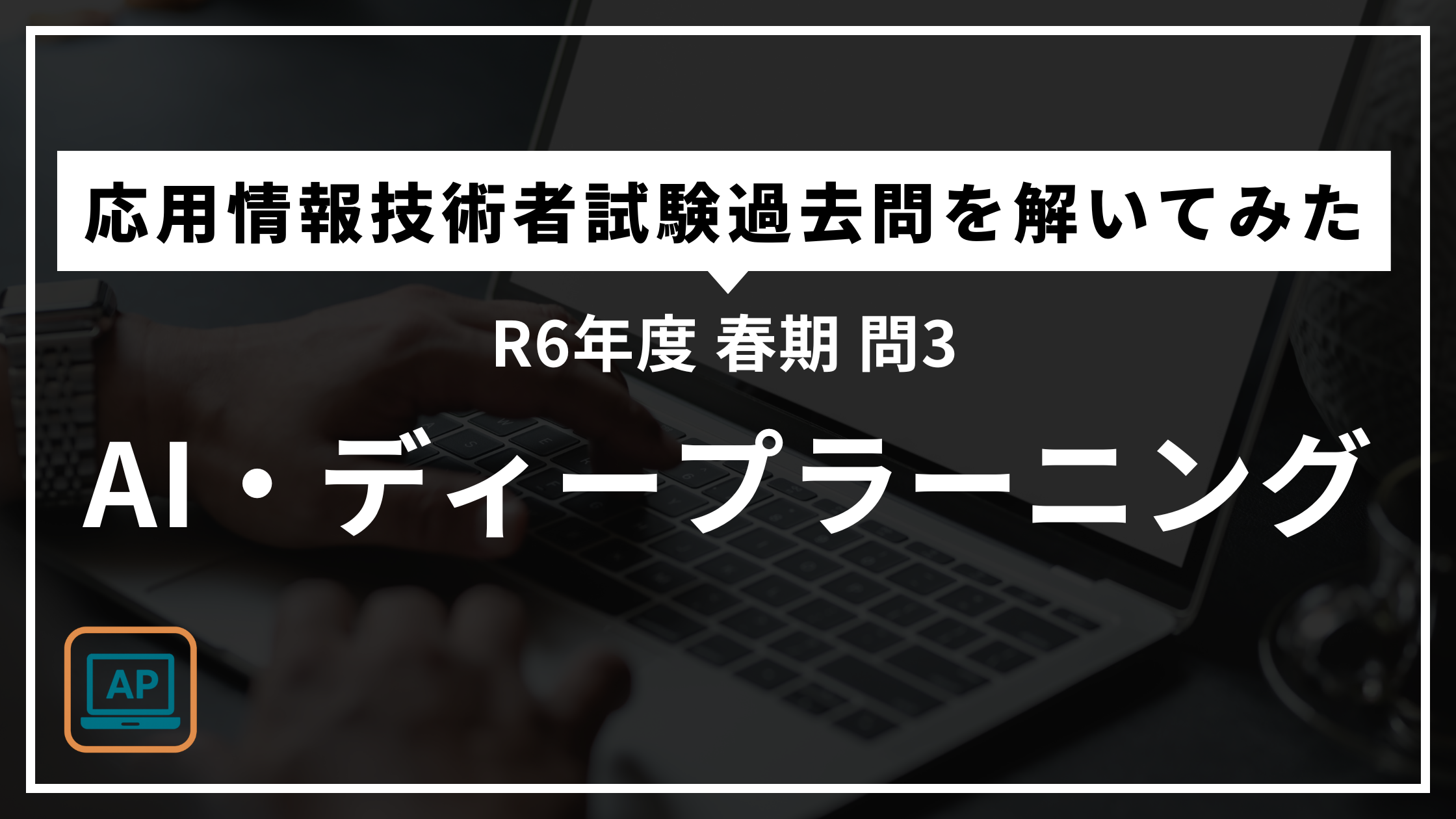
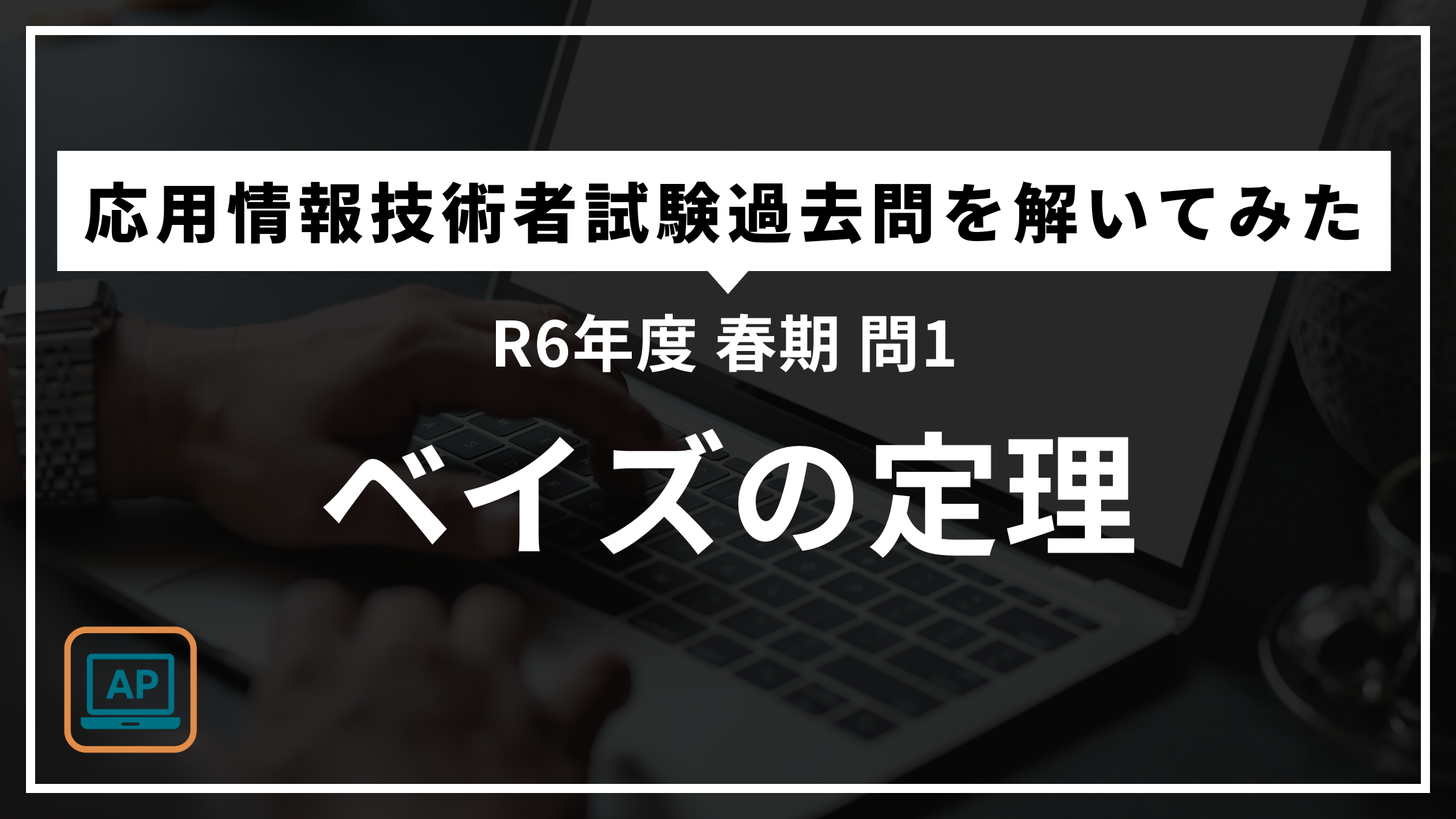
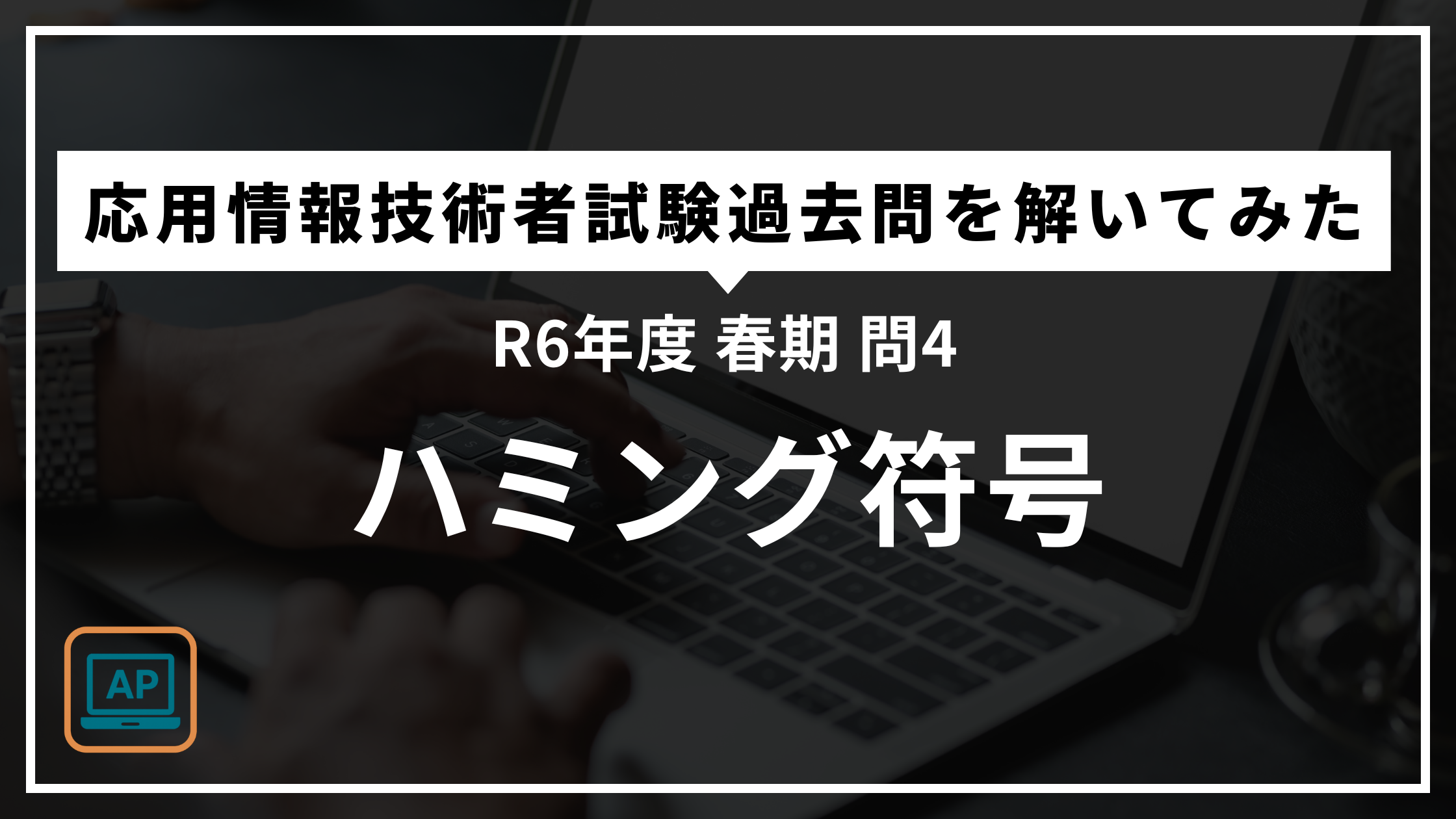
コメント